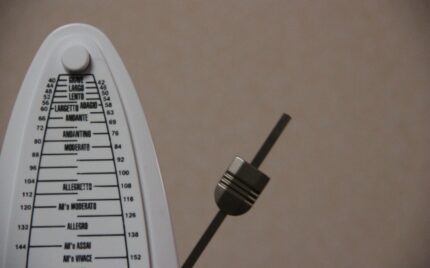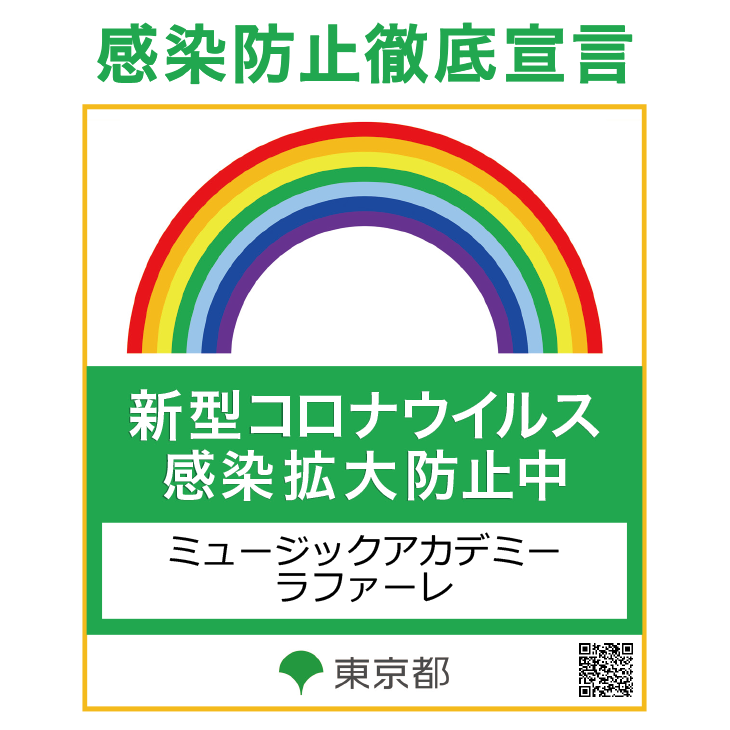「ピアノの詩人」ショパンってどんな人?
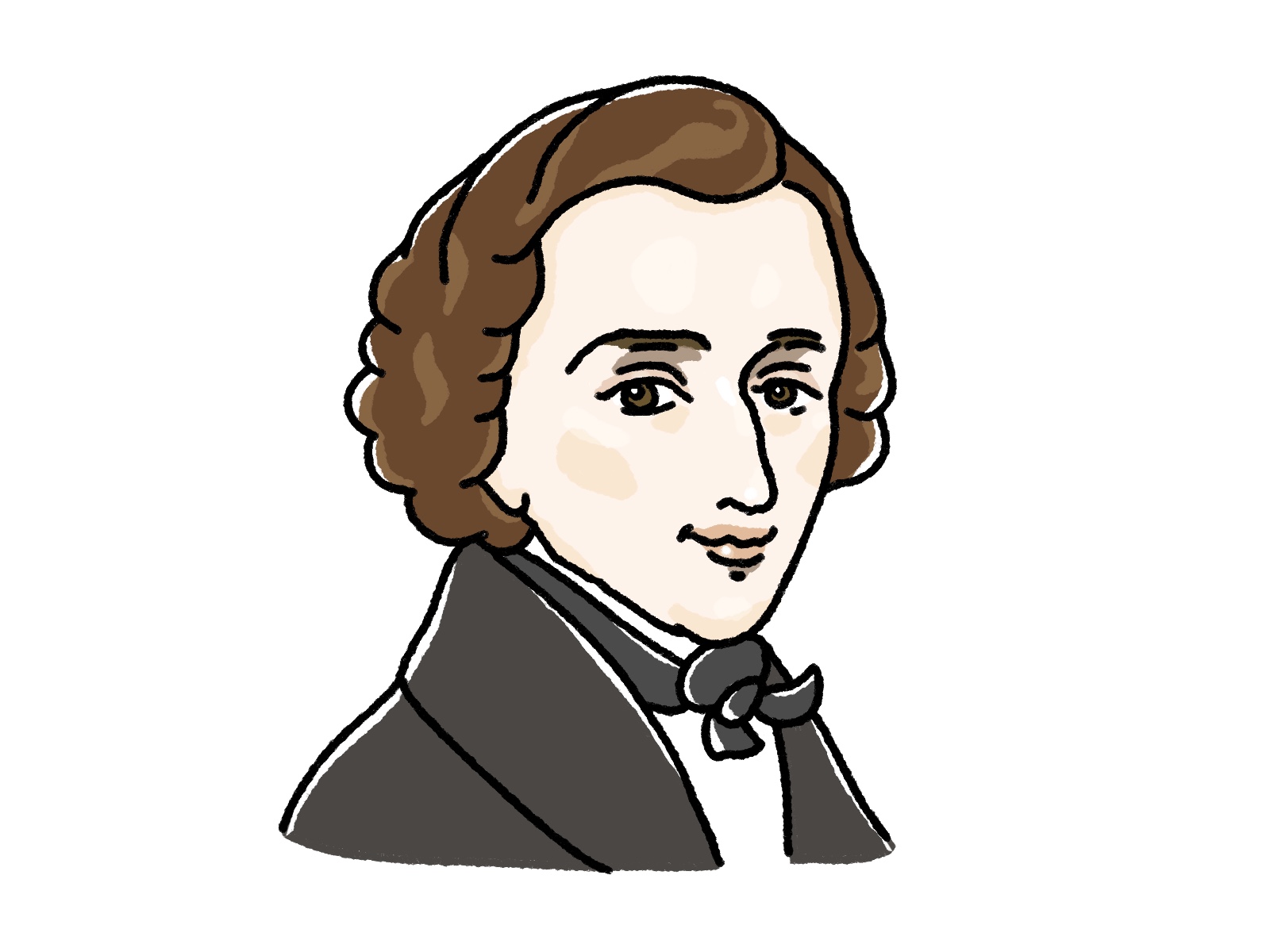
こんにちは!
大塚駅から徒歩2分の音楽教室、ミュージックアカデミーラファーレ ピアノ講師の東出です。
ピアノを習っていると、さまざまな作曲家の名前に出会います。バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン…。その中でも「ショパン」という名前は、音楽に詳しくない方でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
でも、実際にどんな人で、どんな音楽を残したのかを知っている方は案外少ないかもしれません。今回は、ピアノを愛する人なら誰もが一度は弾いてみたくなる作曲家、フレデリック・ショパンをご紹介します♪
ショパンについて
「ショパン」という名前を聞くと、どんなイメージが浮かびますか?
優雅で少し切ないメロディー、夜に静かに流れるピアノの音…そんな印象を持っている方も多いかもしれません。実はショパンは、クラシック音楽の中でも“ピアノの詩人”と呼ばれるほど、ピアノの魅力を引き出した作曲家です。ピアノを習っている子どもたちにとっても、これから大人になってピアノを楽しみたい方にとっても、ショパンの音楽はとても身近で、心に寄り添ってくれる存在なのです。
ポーランドのポーランドに生まれ、パリで活躍した作曲家
 ショパンは1810年、ポーランドのワルシャワ近郊に生まれました。幼いころから音楽の才能を示し、7歳で作曲を始めるほどの早熟ぶり。20歳の頃、自由と文化の都と呼ばれたフランス・パリへ渡ります。そこで多くの芸術家や音楽家と交流しながら、作曲と演奏の療法で活躍しました。(写真はポーランドの街並み)
ショパンは1810年、ポーランドのワルシャワ近郊に生まれました。幼いころから音楽の才能を示し、7歳で作曲を始めるほどの早熟ぶり。20歳の頃、自由と文化の都と呼ばれたフランス・パリへ渡ります。そこで多くの芸術家や音楽家と交流しながら、作曲と演奏の療法で活躍しました。(写真はポーランドの街並み)
ただし、ショパンは大きなコンサートホールで華やかに演奏するよりも、サロンと呼ばれる小さな集まりで弾くことを好みました。近い距離で聴く人の心にそっと触れるような音楽を大切にしていたからです。その繊細な性格と音楽が、今も世界中で愛されている理由のひとつかもしれません。
「ピアノの詩人」と呼ばれる理由
 ショパンの曲は、どれもピアノの魅力を最大限に引き出す工夫にあふれています。音がまるで人の声のように歌い、感情を語りかけてくるように聴こえるのです。
ショパンの曲は、どれもピアノの魅力を最大限に引き出す工夫にあふれています。音がまるで人の声のように歌い、感情を語りかけてくるように聴こえるのです。
代表的な作品としては、「ノクターン(夜想曲)」「ワルツ」「マズルカ」「ポロネーズ」などがあります。
- ノクターンは、夜の静けさや物思いを表すような、ゆったりとした美しい曲。
-
ワルツは、軽やかで優雅な3拍子の踊りの音楽。
-
マズルカやポロネーズは、ショパンの故郷ポーランドの舞曲に由来していて、民族的なリズムが特徴です。
同じピアノでも、弾き方や響かせ方によってこんなにも表情豊かな世界を描けるのかと驚かされます。
ピアノを習う方にも人気!
ピアノを習っていると、いつかはショパンの曲を弾いてみたい!という声をよく耳にします。理由のひとつは、メロディーが心地よく、感情をのせやすいからです。初級から挑戦できる短いワルツやマズルカもあれば、少し難易度が高い曲(バラード、エチュードなど)もあります。成長とともにステップアップしながらショパンを弾けるのも魅力です。
また、ショパンの曲はただ音を並べるだけではなく、「どう表情をつけるか」「どう歌うか」を考える必要があります。テクニックの練習だけでなく、音楽的な感性を育てるのにぴったりです。発表会でも人気が高く、お子さんの成長を感じられるレパートリーの一つです♫
心を動かす音楽の力
 ショパンの音楽には、悲しみや喜び、希望や郷愁など、複雑な感情がそっと込められています。華やかさの中にある繊細さが、聴く人の心を優しく包み込んでくれるのです。大人が疲れたときに聴いても癒やされますし、子どもにとっても気持ちを表現する良いきっかけになります。
ショパンの音楽には、悲しみや喜び、希望や郷愁など、複雑な感情がそっと込められています。華やかさの中にある繊細さが、聴く人の心を優しく包み込んでくれるのです。大人が疲れたときに聴いても癒やされますし、子どもにとっても気持ちを表現する良いきっかけになります。
たとえば、夜寝る前にノクターンを聴けば心が落ち着き、朝の始まりにワルツを聴けば気分が明るくなります。お家で小さくBGMとして流すだけでも、音楽が生活を豊かにしてくれるでしょう。
まとめ
ショパンは遠い昔の人ですが、その音楽は今も変わらず私たちのそばにあります。子どもたちが初めてショパンの曲に挑戦するとき、その音の美しさに驚く顔を見るのは、ピアノを教える喜びのひとつです。名前だけしか知らなかった方も、これを機にぜひショパンの曲を聴いてみてください。きっと心の奥にやさしく響く音に出会えるはずです。