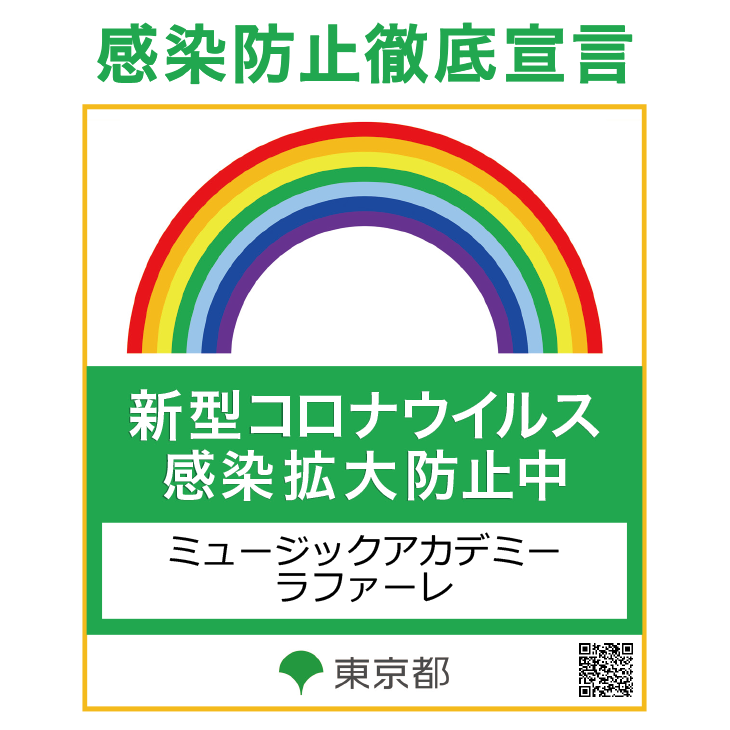足元から音楽を彩る 〜少し応用的なペダル活用術〜

こんにちは!
山手線、都電荒川線大塚駅から徒歩2分、ミュージックアカデミーラファーレ ピアノ講師の新林です。
ピアノの演奏って手の動きに目が行きがちですが、実は足元のペダルこそ、音楽の空気感を決める大きな鍵になっています。基本的な使い方はもちろん大切ですが、
今回はそんなテクニックを少し紹介します!
基本的なペダルの役割等の解説は少し前のブログにあるので、気になる方は是非そちらも見に行ってみてください。
右ペダル ― 響きを生み出す「空間づくりの名人」
右ペダル(ダンパーペダル)は音と音を自然につなげるだけでなく、
半押しペダル(ハーフペダル)
ペダルを一番下まで押し込んでしまうと、曲やそのフレーズによっては雰囲気を台無しにしてしまう事があります。そこで役に立つのがこのテクニックです。ペダルを少しだけ踏み込むことで、完全な響きの持続を避けつつ、
ただし、ピアノのメーカーやそれぞれの個体差によってペダルの効き具合や深さは違うので、そこは要注意です。
刻みペダル(踏み替えペダル)
ショパンやリストなど、音が複雑に動く中でも「
このような曲では和音が次々に変化し、ペダルを踏み続けたまま次の和音に変わってしまうと瞬く間に音は濁ってしまいます。このような時、和音が変わるごとに素早く踏み替えることで響きをクリアに保ちながら持続音を確保できます。
和音の変化が目まぐるしく、ペダルの踏み替えが間に合いそうにない時は、ペダルの踏み込み具合を若干浅くすることで解決できます。
また、これの更に応用版としてビブラートペダルというテクニックがあります。弦楽器や声楽のビブラート程ではありませんが、延ばしている音に対してペダルを素早く上げたり下げたり繰り返すことで、単調な音に変化と表情を与え響きを濁らせることなく広げる事ができます。
踏み遅らせ・離し遅らせのタイミング操作
ペダルは、踏むタイミングによっても大きく違った効果を得られます。例えば、音を弾いた直後に踏む・もしくは弾いた少し後に離すことで、
ラヴェルやドビュッシーの作品では、
逆に強い音を出したい時、ペダルを音を出す瞬間同時に踏み込むことで音量と響きを強くすることもできます。
左ペダル ― 音色を変える「音の化粧師」
左ペダル(シフトペダル、ウナ・コルダ)は、
もともと「ウナ・コルダ=一本弦で」
音色のコントラストづくり
力強く広がった音の直後に左ペダルを使うと、
これによって、音楽に“陰影”や“立体感”が加わり、
段階的な踏み込み調整
左ペダルにも、右ペダルと同様踏み込む段階による変化があり、「少しだけ踏む」「
この中でも、個人的に愛用しているテクニックが左ペダルの半押しです。ピアノを弾く本番というのは、弾き始めるまでどんな響き、音の響き具合というのが分かりません。そんな中で繊細な音から始めたいときにこのテクニックはとても大きな精神的な支えになってくれます。しっかり踏み込む時ほど音を曇らせずに音が飛び出してしまうリスクを軽減してくれます。(調律がちゃんとされていない場合、音が変に響く可能性があるのでそこは要注意です。)
このようなテクニックを活用することで、より微細な音のニュアンス調整が可能になります。
まとめ
ペダルは、音楽に“呼吸”を与えるもの。
耳を澄ませながら丁寧に付き合っていくと、
こうした繊細な踏み方や使い分けができるようになると、ペダルは単なる「響かせる道具」ではなく、“音楽の呼吸や温度”

一音一音がどう響いて消えていくか、
どこまで空間を保ち、どこで断ち切るか――
ほんのわずかな足の動きが、音楽の深さを何倍にも広げてくれる。
そんな“静かな魔法”を、是非試してみてください。